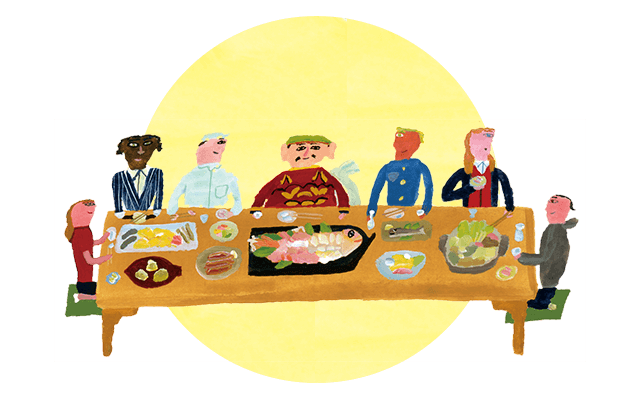
小難しい話

2020.01.22 日本酒づくりに影響するもの

あらゆるものが影響する日本酒造り
全国のさまざまな地で、独自の文化を形成してきた日本酒。ただ現在は、地域ごとに特徴をわけることが非常に難しいとされています。それよりも光るのは、酒蔵ごとの個性。なかでも日本酒の風味に大きな影響を与える「酵母」は、かつて酒蔵ごとに存在し、それぞれ独自の味をつくりあげてきました。酵母が生まれる背景には、酒蔵の湿度や温度、周辺の環境、造る人に付着した微生物など、あらゆるものが影響すると考えられます。
日本酒の味は何が決め手?
では、そもそも日本酒の味はどうやって変わるのでしょうか。それは、人が味を感じる化合物が酒の中に存在するから。化合物は微生物によってつくられるため、種類や比率が変わることによって、そのまま味わいに直結します。微生物に影響を及ぼすのは、湿度や温度、蔵の中の構造、ひいてはなんと掃除の頻度まで。日本酒の味は、環境のすべてがつくりあげていると言えます。
8割を占める重要な資源、水
日本酒にとって「水」は80〜85%を占める、非常に重要な源。硬水は酵母が活発になるため、発酵が旺盛に。対して軟水は酵母がどんどん増えることが少ないため、京都・伏見の「女酒」と呼ばれているような、甘みのある清酒になりやすいとされています。つまり水は風味に影響し、味わいをつくる一つの要因となるのです。日本には多くの水系があり、その水系ごとに水の特徴が異なると考えられます。多くの酒蔵は、その蔵がある場所の水を使用するため、地域性が表されるかもしれません。
播磨という土地
製造技術が発達した現在、地域の持つ風土や地形が清酒の味に与える影響は、昔よりも小さくなっていると考えられます。では、播磨がなぜ日本酒の醸造産地として続いているのでしょうか。理由として挙げられるのは、規模や経営方針が多様な酒蔵が一地域に集まっていること。設備投資の異なる大小の酒蔵、何種類もの酒類を製造する酒蔵に、2、3年寝かせてから出荷する酒蔵など、バラエティーに富んだ蔵元が点在していることが、播磨の酒の魅力へとつながっているのでしょう。



