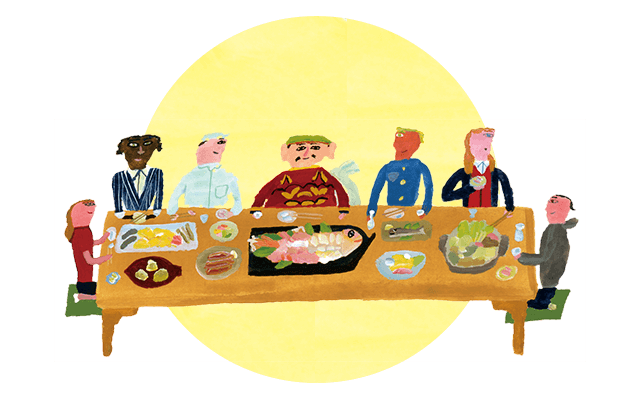
小難しい話

2021.04.01 播磨の食文化が醸成した理由

2点から探る地域の食文化
京都や大阪に近い播磨は都への出荷を見据え、醤油や味噌などのを極めてきました。一方で、他からは馴染みのない特徴を持つ味の発酵食品を作り、自分たちならではの食品を確保してきたという歴史もあるようです。都の味と地元の味を分けることで、自らのアイデンティティを確立してきたのです。2つの視点から、播磨の食文化の礎を探ってみましょう。
醸造に適した地下水の存在
播州平野は扇状地が多く、水はけのよい土地として知られています。よって降った雨が地上に溜まらず、地下に浸透します。瀬戸内海気候は降水量が少ない地域ですが、砂地の下には地下水が流れているのです。さらに冬の乾燥した北風によって表面が乾くので、微生物の発生を抑制、つまりコントロールできる。その上、必要な水は地下から汲みあげることができる。まさに醸造品を作るには恵まれた土地である、ということです。
醸造品の原料となる作物も
奈良〜平安時代。日本に稲作が広まり、全国各地で米づくりが行われるなか、播磨の土地は水はけがよいため、水田ができる場所がいくぶん限られていました。そこで先人たちはわずかな水でできる作物を探し求めた末、大豆や麦の畑作に行き着き、やがて醤油や味噌といった醸造品の原料となる作物が根付いたのです。その後、鎌倉時代に寺社を通して中国伝来の食文化がもたらされ、播磨の持つさまざまな要素が融合し、発酵食品が成り立ちました。
都で磨き上げた味わい
播磨にとって、最大のマーケットは京都でした。当時、家元や大僧正など、文化的権威の象徴が集う京都で「美味しい」と言わしめることは、「日本で一番美味しい」であることと同義。西日本各地のあらゆる産物が北前船に積まれ、大阪へと送り込まれるようすを目前にしていた播磨は、「都で喜ばれる味とはなにか」を見聞きできる位置にあったのです。京料理をベースに捉え、安定した味わいをつくるために磨き上げてきた播磨の醸造品は、当時から抜群の評判を得ていたのです。
関連リンク



