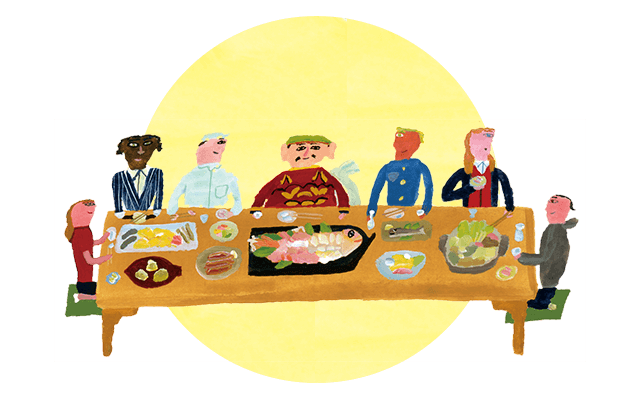
小難しい話

2020.01.22 醤油のふるさと

発祥、かつ日本一
関西の家庭の味に必要不可欠な「うすくち(淡口)醤油」は、播磨が発祥の地であり、日本一の生産地でもあります。さかのぼること天正15(1587)年、丸尾孫右衛門長村が武士を捨てて龍野町(現在のたつの市)で商人になり、「円尾屋」の屋号で酒、醤油の醸造販売を始めたことが起源とされています。
うすくち醤油と甘酒
もともと、龍野は酒造地でした。しかし酒に必要な硬度が足りない軟水だったこと、酵母の無機栄養分が不足していたため、酒造業は廃れていきました。ところが鉄分が少ない龍野の水は、うすくち醤油を醸(かも)すのに最適なことが判明。さらに上質な大豆と塩が手に入りやすかったことから、醤油の産地へ。さらに龍野のうすくち醤油には甘酒が用いられており、この醸造法は寛文年間(1661〜1673年)に発案されたとされています。ただ以前より酒造業が盛んな地域だったことから、甘酒の使用の根源は、もっと古くからあったとも言われています。
広がる醤油文化
龍野醤油はその後、龍野藩の手厚い保護のもと発展していきます。享保9(1724)年には、龍野藩から江戸に送る醤油が112石から毎年増え、わずか6年後には162石にまでになったという記録も残されています。また円尾屋文章によると、京都に初めて送られたのは元文年間(1736〜1741年)の頃。揖保川(いぼがわ)の水運を利用した船便で、網干港から京都、大阪の大消費地への輸送ルートに恵まれていたこともあり、産業を発展させ、現在の近畿を中心としたうすくち醤油文化圏が形成されました。城下町としての面影が残り、播磨の小京都とも呼ばれているたつの市には、現在も複数の醤油製造会社が点在しています。
醤油をつくる
高品質な醤油づくりに、微生物の力は欠かせません。まずは厳選された大豆、小麦、塩、米などの材料をそれぞれ、微生物が働きやすいように炒ったり蒸したりすることから。そこから蒸しあがった大豆と挽き割った小麦を混合し、菌を加えることで麹(こうじ)を生成。そこに塩水を加えて約半年間発酵・熟成させ、もろみをつくります。これを搾れば、生醤油のできあがりです。
うすい色の理由
うすくち醤油はその名の通り、色のうすさも大切な要素。軟水で雑味の少ない揖保川の水に、そのヒントがありました。軟水とは、カルシウムやマグネシウム、鉄分が非常に少ない水のことで、醤油の色を濃くしない特性を持っています。まただしのうまみが出やすく、煮物などの調理にも最適。この色合いを生み出すためには、微妙な温度調節や、酵素に触れさせない配慮など、機械まかせにはできない繊細さを持っているのです。



